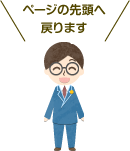県西支部会員の活動
元仙台家庭裁判所長による離婚事件研修会 Vol.5
令和6年11月1日、元仙台家庭裁判所長である秋武憲一先生を講師にお招きし、共同親権に関する研修会を当支部にて実施しました。
昨年に引き続き秋武先生をお招きし、5回目となる今回の研修会にも多数の支部会員が参加しました。
今回の研修会のテーマは、「共同親権」についてでした。令和6年5月24日に、共同親権制度を柱とする民法の改正法が公布され、公布後2年以内、すなわち、令和8年5月24日までには同制度が開始されます。今後の実務に大きな影響を与えうる点で、実務家として多くの会員が関心を持っているテーマについて扱っていただきました。

現行の民法では、婚姻中は父母が共同で親権を行使しますが、離婚後は単独親権となるのが原則です。これは、離婚により別々の生活をする父母が共同で親権を行使することが通常は困難であり、子どもの利益を害することになると考えられていたためです。
しかし、このような考え方は昭和22年に現行民法が施行された当時の考え方であり、近年では離婚後の父母の関係や、子どもの養育環境も多様化し、法務省の調査でも諸外国のほとんどが共同親権制を導入しているという事実があります。このような時代の流れや世界各国の情勢を踏まえて、今回の民法改正がなされました。
秋武先生には、共同親権をはじめとする法改正の内容及び今後の実務における展望などについてお話しいただきました。
民法改正後は、未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、親権について単独親権とするか、共同親権とするかを協議により決定する、選択的共同親権制が導入されます。もし協議による親権者の決定ができない場合には、現行制度では親権者の協議ができない限り離婚ができませんでしたが、改正後は、親権者の決定を求める家事調停または審判の申立てを行い、離婚の届出をすることで、協議離婚ができることになりました。この場合は、裁判所が親権者の決定をすることになります。また、それに伴い、協議離婚ができたとしても養育費の金額が定まっていない事態が発生しうるため、金額については「法定養育費」という形で定めた金額を支払うものとされています。このように、親権や養育費について取決めができないことで、離婚自体ができなくなってしまうという事態を解消する改正がなされています。
その反面、今後の運用については課題も出てくることが想定されます。当事者の協議で単独親権・共同親権のいずれとするかを決められない場合は、裁判所がそれを決めることになりますが、共同親権の是非や内容については、法律の規定上は「子どもの利益」しか指針がないため、その判断に困難を極める可能性があります。この点に関しては、裁判所だけでなく、弁護士が相談を受け、依頼を受ける場合も同様の課題となります。
そこで、今後も共同親権に関する勉強会や、実際の事例をもとにしたケース研究を積み重ねることで、共同親権についての共通認識を形成していくことが不可欠となります。
本研修会で秋武先生より共同親権についてお話しいただき、法改正について理解を深めるとともに、今後の共同親権の運用に関する課題を改めて自覚する、大変有意義な研修となりました。

今回の研修会を契機として、共同親権に関する研鑽を積み、今後の共同親権の動向に適切に対応できるように努めて参りたいと思います。
以上