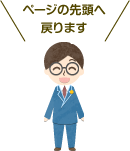県西支部会員の活動
税理士会と合同研修会を行いました。
昨今、税理士が行った税務申告に対し、課税庁から増額更正処分(簡単に言うと、納税額の増額を求められる処分のことです)を課されることが増えています。これに伴い、税務申告を担当した税理士が、その依頼者から損害賠償請求訴訟(略して、「税賠訴訟」と呼びます。)を提起されるという事例も増えてきています。
依頼者としては、自身が信頼して当該税理士に依頼したのに、その税理士が行った税務申告が原因で、当初に想定していたよりも高額な納税額を課されてしまうことに納得がいかず、責任を問うために訴訟提起を選択しているといえます。
一方で、税理士の立場からすると、例えば少しでも納税額を低く押さえたいという依頼者の意向に沿うため、関連法規等に基づいて従前と同様の申告を行ったにもかかわらず、課税庁の解釈変更などの理由で、突然、納税の増額処分を課されてしまっては、自信を持って日々の申告業務を遂行することが困難となってしまいます。
このような訴訟リスクに備えるためには、どういった税務申告事例に対して増額の更正処分が下されているかを把握するとともに、税理士が実際に訴訟を提起された場合に裁判所が下した判断の内容を理解しておくことが効果的です。
そこで、令和6年11月13日に東京地方税理士会小田原支部及び同平塚支部と合同で、税賠訴訟を数多く手がけている弁護士を講師にお招きして、「最近の税務訴訟事件の事例紹介と税賠訴訟事件の実際」というテーマでセミナーを開催しました。

セミナーでは、収益物件(賃貸用マンション)や取引相場のない株式の評価に関して裁判所が下した判断について理解するともに、実際の税賠訴訟判決の解説を通じて、税理士が依頼者に対して負う具体的な法的義務(善管注意義務)の内容についても理解を深めることができました。
神奈川県弁護士会県西支部では、今後も、定期的に税理士会との合同研修会を開催してともに研鑽を積みながら、地域住民の皆さまに良質な法的サービスを提供できるよう努めて参ります。